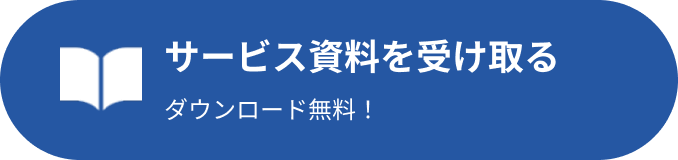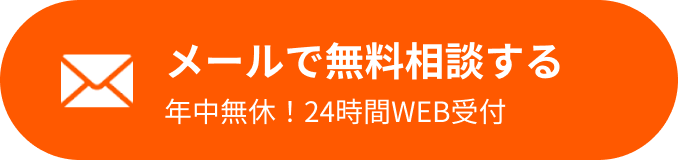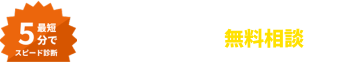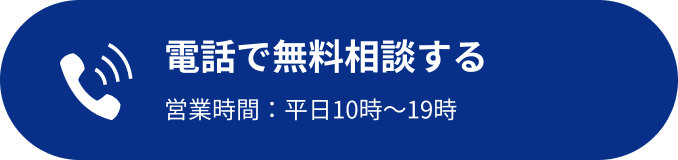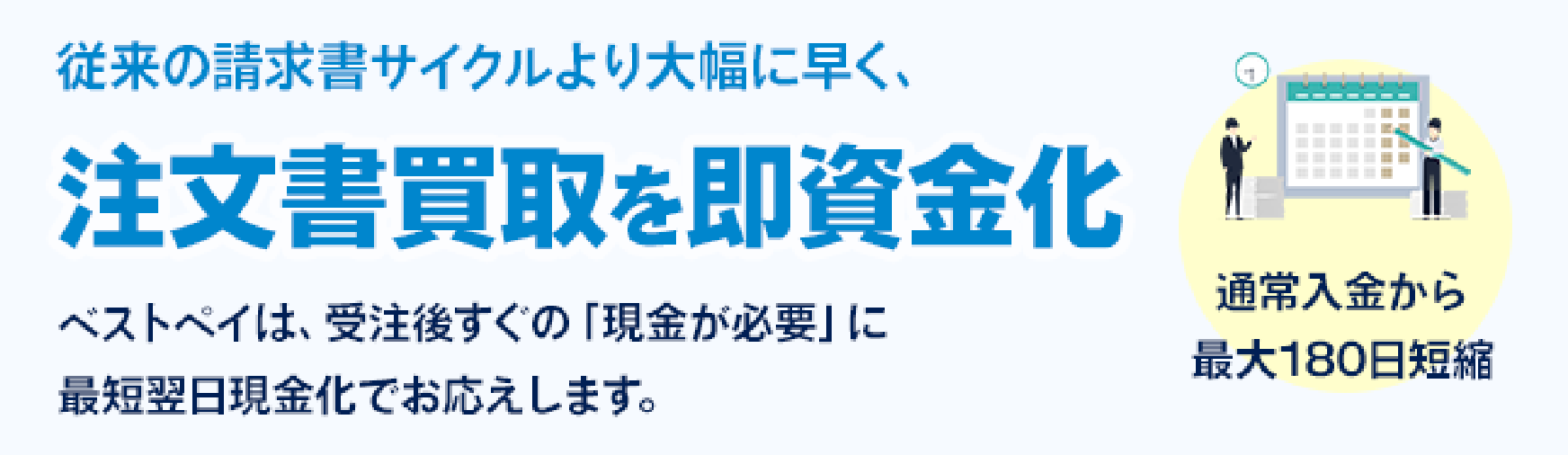会社の借り入れは事業において不可欠ですが、担保や保証の違いなどによってさまざまな種類があります。また、借り入れできる金融機関も銀行以外にさまざまあるため、自社に合った選択をすることが大切です。
この記事では、会社の借り入れについて、種類や借り入れできる金融機関、利用の流れや借り入れを成功させるポイントを解説します。
会社の借り入れの種類
会社の借り入れは、担保や保証の違いなどによって以下のように分類されます。これらの借り入れの内容を理解して、適切な手段を利用することが大切です。
ビジネスローン
ビジネスローンは、原則担保なしで借り入れできる事業用ローンのことです。
担保にできる資産をあまり保有していない中小企業や個人事業主、スタートアップ企業などでも利用しやすい借り入れ手段となっています。
ビジネスローンの用途は事業目的であれば制限はなく、運転資金・設備投資・仕入・つなぎ資金など幅広く利用可能です。そして、個人向けのカードローンと同様に、限度額の範囲内なら再審査なしで何度も借り入れできます。
なお、何度も借り入れできないタイプのビジネスローンは「フリーローン」と呼ばれます。
ビジネスローンのメリット
ビジネスローンの主なメリットは、審査のハードルが低く、入金スピードが早いことです。
最短即日から数日程度で入金可能なローンも多く、有担保ローンでは間に合わない急ぎの資金調達にも対応できます。
ビジネスローンのデメリット
金利が高く借入可能額が低いのが、ビジネスローンのデメリットです。
ビジネスローンの上限金利は14%から18%程度で、個人向けのカードローンと変わらない水準となっています。
そして、借入可能額は最大で500万円から1,000万円程度のことが多く、有担保のローンに比べると低い傾向があります。
また、ビジネスローンの借り入れが多いと、銀行融資の審査で不利になる場合があるのもデメリットの一つです。
ビジネスローンの基本情報まとめ
ビジネスローンの金利や融資スピードなどの基本情報をまとめると、以下のとおりとなります。
| 金利 |
|
|---|---|
| 融資スピード |
|
| 借入限度額 |
|
| 審査難易度 |
|
不動産担保ローン
不動産担保ローンとは、不動産(主に土地と建物)を担保に借り入れするローンです。資金の使途は事業用なら幅広く可能で、利便性の高い借り入れ手段の一つだといえます。
不動産担保ローンは担保によって金融機関のリスクが低くなるので、ビジネスローンより低金利で高額の借り入れが可能です。また、返済期間を長く設定できる(最大30年程度)のもメリットといえます。
一方、手続きが多く入金まで手間と時間がかかることや、返済が滞ると最終的には不動産を差し押さえられる可能性があるのは注意点です。
借り入れ時の諸費用に注意
不動産担保ローンはビジネスローンより低金利ですが、借り入れ時に諸費用が発生するのが注意点です。
諸費用は合計で借り入れ額の数パーセント程度かかることが多いので、利息と諸費用の合計額(実質年率)が許容範囲であるかを検討しましょう。
不動産担保ローンで発生する主な経費は以下のとおりです。
- 金融機関に払う事務手数料
- 契約書にかかる印紙税
- 不動産の登記費用
- 登記手続きにおける司法書士への報酬
- 不動産の調査料
- 火災保険料
不動産担保ローンの基本情報まとめ
不動産担保ローンの基本情報をまとめると、以下のとおりとなります。
| 金利 |
|
|---|---|
| 融資スピード |
|
| 借入限度額 |
|
| 審査難易度 |
|
信用保証協会付融資
信用保証協会付融資とは、「信用保証協会」という機関が保証人の役割を果たす借り入れ方法です。もし返済が滞った場合は、信用保証協会が立て替えて金融機関に返済します(代位弁済)。
信用保証協会付融資を利用すれば、信用の低い中小企業やスタートアップ企業でも融資を受けやすくなります。
総務省のデータによると、中小企業と小規模事業者の約44%が信用保証協会付融資を利用しており、中小企業等にとって借り入れの主要な選択肢の一つとなっています。
信用保証協会付融資の注意点
信用保証協会付融資は中小企業等にとってメリットが大きい借り入れ方法ですが、いくつか注意点もあります。注意点を理解したうえで、信用保証協会付融資を有効活用することが大切です。
主な注意点は以下のとおりです。
【借金が帳消しになるわけではない】
返済が滞って信用保証協会が代位弁済した場合、金融機関への返済はなくなりますが、代わりに信用保証協会に返済する必要があります。代位弁済は借金を帳消しにするものではありません。
【保証料がかかる】
信用保証協会付融資は、金融機関に支払う利息に加えて、信用保証協会に保証料を支払う必要があります。保証料は年利0.3%から2%程度の間で決められます。
【審査に時間がかかる】
信用保証協会付融資では、金融機関と信用保証協会両方の審査を受けるため、審査に時間がかかる傾向があります。
【規模の大きい会社は利用できない】
信用保証協会付融資は、資本金と従業員数が一定以下の会社しか利用できません。業種などによって、資本金が5,000万円から3億円以下、従業員数が5人から900人以下が条件となります。
【利用できない業種がある】
農業・林業・漁業・金融業・保険業は、原則として信用保証協会付融資を利用できません。なお、居酒屋・スナック・パチンコ店等は以前は利用不可でしたが、2020年に利用可能業種に追加されています。
信用保証協会付融資の基本情報まとめ
信用保証協会付融資の基本情報をまとめると、以下のとおりとなります。
| 金利 |
|
|---|---|
| 融資スピード |
|
| 借入限度額 |
|
| 審査難易度 |
|
プロパー融資
プロパー融資は、信用保証協会を利用しない銀行融資のことです。
プロパー融資は、もし返済が滞っても信用保証協会の補償を受けられないため、銀行にとってリスクが大きくなります。
そのため、プロパー融資は審査が厳しく、業績が好調で銀行との取引実績が十分でないと、借り入れできないことが多いです。
中小企業やスタートアップ企業の利用は難しいことが多く、主に中堅・大企業向けの融資方法となります。
その代わりに、プロパー融資は信用保証協会への保証料が不要で、融資額の制限がないのがメリットです。また、プロパー融資に通った実績は、会社の信用力の高さを示す指標にもなります。
プロパー融資の基本情報まとめ
プロパー融資の基本情報をまとめると、以下のとおりとなります。
| 金利 |
|
|---|---|
| 融資スピード |
|
| 借入限度額 |
|
| 審査難易度 |
|
動産担保融資
動産担保融資(ABL(Asset Based Lending))とは、不動産以外の資産を担保にする融資です。
動産担保融資では、売掛債権・在庫・原材料・設備・機械・車両など、さまざまな資産を担保にすることが可能です。担保にできるような不動産を持っていない会社でも、利用できるのがメリットだといえます。
なお、売掛債権を担保にする動産担保融資を、特に「売掛債権担保融資」と呼ぶこともあります。
信用保証協会の保証をつけることも可能
信用保証協会は、動産担保融資に対する保証も提供しています。
内容は不動産担保ローンの場合と同様で、保証料を支払うことで、返済不能になった時に代位弁済を行います。
返済不能が倒産に結び付きやすい
動産担保融資も不動産担保ローンと同様、返済が滞ると最終的には担保が処分されて弁済に充てられます。
ただし、不動産と違って、在庫などの動産は日々の営業活動に不可欠なものが多いため、差し押さえられると事業の継続が困難になるケースも考えられます。
よって、動産担保融資は不動産担保ローンに比べて、返済不能が倒産に結び付きやすい性質があるといえます。
動産担保融資の基本情報まとめ
動産担保融資の基本情報をまとめると、以下のとおりとなります。
| 金利 |
|
|---|---|
| 融資スピード |
|
| 借入限度額 |
|
| 審査難易度 |
|
会社の借り入れの形態
会社の借り入れの形態は証書貸付が最も一般的ですが、他にも手形貸付や当座貸越といった形態もあります。
- 証書貸付
- 手形貸付
- 当座貸越
証書貸付
証書貸付とは「金銭消費貸借契約」を締結して行う貸付のことです。契約書に返済額や金利、返済期日などを記載して、契約内容にしたがって返済していきます。
多くの会社の借り入れ、および個人向けの借り入れは、証書貸付で行われます。
手形貸付
手形貸付とは、借り手が金融機関に手形を発行(振出し)して、それを担保にする借り入れ方法です。
手形には金額と支払期日などが記載されており、記載金額から利息を引いた額を借り入れることができます。そして支払期日が来ると、借り手の口座から借り入れ額と利息が引き落とされて返済されます。
電子的な手形である「でんさい」でも、紙の手形と同様の方法で借り入れが可能です(でんさい貸付)。紙の手形は2027年に廃止予定なので、その後はでんさい貸付に移行することになると考えられます。
入金スピードが早い
手形貸付は不動産担保ローンなどより手続きが簡便で、数日から1週間程度で借り入れ可能です。入金スピードの早さは、手形貸付のメリットだといえます。
長期の借り入れはできない
手形貸付の支払期日はおおむね1年以内で、長期間の借り入れができないのはデメリットです。また、返済は原則として一括払いで、分割払いはできません。
そのため手形貸付は、主につなぎ資金や短期的な運転資金などで利用することになります。
不渡りは倒産につながる
手形は6カ月間に2回返済が遅れる(不渡り)と、ほぼ全ての銀行と2年間取引ができなくなります。
銀行と取引できないと、ほとんどの場合事業の継続は困難になるため、2回の不渡りを「事実上の倒産」と呼ぶこともあります。
手形貸付を利用する際は、期日に必ず返済できるよう計画しておくことが重要です。
当座貸越
当座貸越とは、借入限度額の範囲内で、必要な時に必要な額を何度も借り入れできる融資方法です。
不動産担保ローンを始めとする他の多くの融資では、融資額を一度にまとめて借り入れて、後は返済していくのみとなります。
一方、当座貸越では、極度額(借入限度額)の全額を一度にまとめて借りる必要はなく、極度額の範囲内でその都度必要な額だけ借りることができます。
急な出費の備えに利用できる
当座貸越は、急な出費の備えに利用できるのがメリットです。
突発的なトラブルによる出費や、季節要因等による一時的な支出の増加などに対して、素早く対応できます。
金利はやや高い傾向がある
当座貸越の金利は、不動産担保ローンなどと比べてやや高い傾向があるとされています。
ただし、当座貸越は必ずしも極度額を満額借りるわけではないので、支払う利息が高くなるかは借り入れ額と返済期間によります。
約定返済がないものもある
ほとんどの融資では、毎月定められた額を返済する「約定返済」がありますが、当座貸越は約定返済がないものもあります。
約定返済がない当座貸越では、元金は好きなタイミングで返済できるため、返済の自由度が高くなります。
ただし、元金を返済せず借り入れが長引くと、その分利息の支払いが増えるので、計画的に利用することが大切です。
信用力のアピールになることもある
当座貸越は借り入れと返済の自由度が高いため、金融機関にとってはリスクの高い商品です。よって、当座貸越は審査が厳しい傾向があるとされています。
そのため、当座貸越を利用しているという事実が、金融機関から高い信用を得ている証拠とみなされ、会社の信用力のアピールになることもあります。
会社の借り入れができる金融機関等の種類
会社の借り入れができる金融機関等には、銀行以外にも下記のようなものがあります。それぞれの特徴を理解して、適した金融機関等を利用することが大切です。
- 銀行
- 信用金庫・信用組合
- 日本政策金融公庫
- 地方自治体の制度融資
- 消費者金融・信販会社・クレジットカード会社
銀行
銀行とは、銀行法にもとづいて営業している金融機関のことです。貸付や預金を始め、お金に関する幅広い業務を行っています。
銀行には主に、全国に展開している「都市銀行」または「メガバンク」と、地域密着型の「地方銀行」があります。他にも、「信託銀行」「ネット銀行」「ゆうちょ銀行」などが存在します。
多くの銀行は事業者向けの融資を提供していますが、一部のネット銀行やゆうちょ銀行など、提供していない銀行もあります。
都市銀行・メガバンク
都市銀行とは、全国規模で展開する大手銀行のことです。財務省の公式サイトによると、「りそな銀行」「埼玉りそな銀行」「みずほ銀行」「三井住友銀行」「三菱UFJ銀行」の5行が都市銀行であるとされています。
そして、「メガバンク」は非常に規模が大きい銀行を指す用語で、都市銀行とおおむね同じ意味です。三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行を「3大メガバンク」、りそな銀行と埼玉りそな銀行を加えた5行を「5大メガバンク」と呼びます。
都市銀行・メガバンクは、主に大企業や中堅企業に対して、大規模で低金利な融資を行うのが特徴です。一方、中小企業に対する融資はあまり行わない傾向があります。
地方銀行
地方銀行とは「全国地方銀行協会」に加盟している銀行のことで、「第一地方銀行」とも呼びます。そして、「第二地方銀行協会」に加盟している銀行を「第二地方銀行」と呼びます。
地方銀行の代表例は「千葉銀行」「横浜銀行」「静岡銀行」など、第二地方銀行の代表例は「北洋銀行」「京葉銀行」「名古屋銀行」などです。
2025年9月時点で、地方銀行は61行、第二地方銀行は36行存在します。
なお、地方銀行は正確には第一地方銀行のみを指す用語ですが、慣習的に第一地方銀行と第二地方銀行をまとめて「地方銀行」と呼ぶこともあります。
地方銀行は地域密着型のサービスが特徴で、主に地元の中小企業や個人事業主に対して、比較的小規模な融資を行います。特に、第二地方銀行はより小規模な融資を行うことが多い傾向があります。
信託銀行
信託銀行とは、融資や預金などに加えて、資産運用や不動産売買の仲介など、普通の銀行では行わないより幅広い業務を行う銀行です。
代表的な信託銀行には、「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」「みずほ信託銀行」などがあります。
信託銀行が事業資金融資を行うことは一般的ではありませんが、「シンジケートローン」や「ストラクチャードファイナンス」など、専門性の高い資金調達手段を得意にしている傾向があります。
ネット銀行
ネット銀行は実店舗を持たない銀行で、主にネットを通してサービスを提供します。「楽天銀行」「住信SBIネット銀行」「PayPay銀行」などが、ネット銀行の代表例です。
ネット銀行は事業者向けの融資を行っていないことが多いですが、GMOあおぞらネット銀行やPayPay銀行など、一部提供している銀行もあります。
ネット銀行の借り入れはオンライン完結で行えることが多く、手続きが簡潔で入金が早いのが特徴です。一方、借入限度額が低く、金利が高い傾向があります。
また、ネット銀行の事業者向け融資はビジネスローンが中心で、他の銀行に比べて借り入れの選択肢は少なくなります。
信用金庫・信用組合
信用金庫・信用組合は、会員・組合員の出資で運営される非営利の金融機関です。地域の中小企業や個人事業主に融資を行い、地域経済の発展を支援します。
信用組合は信用金庫に比べて対象地域がより限定的で、より小規模な事業者を対象とする傾向があります。
信用金庫・信用組合の融資は、原則として会員・組合員のみを対象としています。会員・組合員の資格は従業員数300人以下などの条件があるため、大企業や中堅企業は利用できません。
信用が低く銀行の融資が通りにくい小規模な事業者にとって、信用金庫・信用組合は主要な借り入れ先の一つとなります。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、国の出資で運営されている非営利の金融機関です。
営利目的の民間金融機関では融資が難しいケースにも対応し、民間金融機関の業務を補完することなどを目的に運営されています。
日本政策金融公庫の融資は金利が低いのに加えて、銀行融資に劣らない高額の借り入れも可能です。まだ実績がないなどの理由で銀行融資が通りづらい事業者にとって、借り入れの主要な選択肢の一つとなります。
民間金融機関の補完の意味合いが強い融資の主な例としては、セーフティーネットのための融資や、創業支援の融資などがあります。実際はこれら以外にもさまざまな融資があるので、有効活用することが大切です。
セーフティーネットのための融資
日本政策金融公庫は、業績が悪化している事業者や、倒産またはそれに近い状態にある事業者に対して、再生のための融資を提供しています。
例えば、民事再生や私的整理を行っている事業者でも、条件を満たせば融資を受けることが可能です。
他には、災害の被害を受けた事業者の、復旧のための融資も提供しています。特に、東日本大震災や能登半島地震などについては、個別の融資制度が設けられています。
創業支援の融資
日本政策金融公庫は、創業時または創業間もない事業者への融資が充実しています。創業時は実績がなく銀行融資が通りにくいため、日本政策金融公庫の活用が有用です。
日本政策金融公庫では、一般的な創業融資以外にも、以下のようなケースごとの創業融資を提供しており、きめ細かい支援が可能となっています。
- 女性の創業支援
- 35歳未満の方の創業支援
- 55歳以上の方の創業支援
- 過去に廃業歴がある方の創業支援
地方自治体の制度融資
地方自治体では、「制度融資」という融資を実施しています。
制度融資とは、地方自治体と金融機関、信用保証協会の3者が連携して行う融資です。
自治体が金融機関に預託している資金を元に、金融機関が信用保証協会付融資を行います。
信用保証協会付融資は原則として上限が2億8,000万円ですが、制度融資はそれとは別枠になるため利用しやすいのが特徴です。
制度融資の具体的な内容は自治体によって異なるため、会社の所在地の自治体でどのような制度融資を実施しているか確認しましょう。
制度融資のメリット・デメリット
自治体の制度融資は、通常の信用保証協会付融資を受けるのが難しい事業者でも、融資を受けられる可能性があるのがメリットです。
一方、自治体・金融機関・信用保証協会の3者が連携するため、手続きに手間がかかり入金スピードが遅い傾向があります。
また、制度融資は主に中小企業や個人事業主を支援する制度なので、規模の大きい事業者は利用できません。
消費者金融・信販会社・クレジットカード会社
消費者金融・信販会社・クレジットカード会社(いわゆる「ノンバンク」)は、主にビジネスローンを提供しています。
ここで消費者金融とは、主に個人や小規模な事業者向けに少額の融資を行う貸金業者のことです。代表的な消費者金融には、「アイフル」「アコム」などがあります。
そして信販会社とは、クレジットカード発行やローンの提供などを主な業務とする金融機関のことです。代表的な信販会社には、「オリコ」「クレディセゾン」などがあります。
そしてクレジットカード会社とは、クレジットカードの発行や決済などを主な業務とする金融機関のことです。代表的なクレジットカード会社には、「三井住友カード」「JCB」などがあります。
ノンバンクのビジネスローンは、銀行のビジネスローンに比べて審査に通りやすく、入金スピードが早い傾向があります。
一方、金利は比較的高く、借入可能額が低い傾向があるのがデメリットです。
会社の借り入れの流れ
会社の借り入れの詳細な流れは、借り入れの種類や利用する金融機関などによって違いますが、大まかな流れはおおむね以下のように進んでいきます。
会社の借り入れをスムーズに行うためには、流れを把握しておくことが大切です。
- 事前相談
- 書類の準備
- 申込み・審査
- 契約・入金
1.事前相談
主にプロパー融資と信用保証協会付融資においては、借り入れの申し込みをする前に、まずは金融機関等に事前相談を行います。
事前相談をすることで、後の手続きをスムーズに進められるとともに、審査に通る可能性を高める効果も期待できます。
事前相談で分かること
事前相談では、融資に関する疑問点を、基礎的なものも含めて全て質問して解決しておくべきです。例えば、以下のような事項について、分からない点を解決しておきましょう。
- 融資の内容に関する基本事項
- どの融資を利用すべきか
- 審査に通る見込み等
- 審査に通るためにすべきこと
【融資の内容に関する基本事項】
金利や返済方法を始めとする、借入れを検討している融資の基本的な内容については、事前相談で明確にしておきましょう。また、融資の申込条件に合致しているかどうかも、あわせて確認しましょう。
【どの融資を利用すべきか】
金融機関が提供する融資にはさまざまな種類があるため、それらの中からどの融資を利用すべきかについて、自社の状況を加味しながらアドバイスしてもらえます。
【審査に通る見込み等】
審査に通る見込みがあるか、見込みがあるならどれくらいの額を借り入れできそうか、および金利を始めとする返済条件の見込みなどを提案してもらえます。
【審査に通るためにすべきこと】
審査に通る確率をより高めるために、何をすべきかといったアドバイスも受けられます。例えば、より説得力のある事業計画書の作成支援、自社の状況を考慮した返済プランのアドバイスなどが得られます。
相談先
事前相談は、初回の借り入れの場合は、借り入れを行う金融機関の相談窓口で行います。すでに取引がある金融機関の場合は、担当者に直接相談すればよいでしょう。
なお、信用保証協会付融資を申し込む場合は、信用保証協会の窓口で相談することも可能です。また、日本政策金融公庫のいわゆる「マル経融資」を申し込む場合は、商工会や商工会議所でも相談できます。
相談方法は、金融機関等に直接出向いて相談する方法と、専用ダイヤル等からの電話での相談、およびオンラインでの相談があります。
なお、事前相談はあらかじめ予約を入れておいたほうが、待ち時間が発生せず便利です。
用意する資料
事前相談ではまだ申し込みは行いませんが、会社の財務状況や事業内容が分かる資料を持っていくと、担当者もアドバイスを行いやすくなります。
例えば、決算書や資金繰り表、事業計画書などが用意できるなら、持参していくとよいでしょう。
また、会社のパンフレットや製品カタログなどを用意すると、担当者が事業内容を把握しやすくなります。
2.書類の準備
事前相談の結果融資の申し込みを決定したら、次は必要な書類を準備します。
具体的にどの書類が必要かは事例によりますが、一般的には以下のような書類が必要になることが多いです。
【基本的な必要書類】
- 本人確認書類
- 決算書・確定申告書(直近2,3期分程度)
- 納税証明書
- 印鑑証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
【計画書等】
- 事業計画書
- 資金繰り表
- 資金計画書・借入計画書
- 創業計画書(創業融資の場合)
- 試算表(創業融資の場合、または決算月から時間が経っている場合など)
【場合によっては必要になる書類】
- 見積書など(設備投資を行う場合)
- 登記事項証明書(担保がある場合)
- 許認可証(許認可が必要な業種の場合)
3.申込み・審査
必要書類を準備したら、借り入れの申込みと審査を行います。
定量評価と定性評価
融資の審査には、財務諸表などの数値から返済能力を評価する「定量評価」と、数値には表れない部分を評価する「定性評価」があり、両者を総合的に判断して融資の可否が決定されます。
定量評価では、自己資本比率などの財務指標をもとに、財務分析ツールなども使って評価するといわれています。
そして定性評価では、経営者の人柄や熱意、事業の将来性、業界動向、同業他社の状況などをもとに、融資担当者が主観も交えて判断します。
定量評価と定性評価をそれぞれどれくらい重視するかについては、詳細は非公開です。しかし一般的には、メガバンクは定量評価をより重視し、地方銀行や信用金庫は定性評価も比較的重視する傾向があるといわれています。
現地調査が行われることもある
融資の審査では、定量評価と定性評価に加えて、融資担当者が会社のオフィスや店舗等に出向く現地調査が行われることもあります。
現地調査では、店舗や設備等の確認、および立地・周辺環境などを確認します。
店舗や設備の内容が提出資料の記載と違う場合や、そもそも店舗や設備が存在していない場合などでは、現地調査で融資が不可となる可能性もあります。
また、家族向けの商品・サービスなのに店舗の周辺がオフィス街であるなど、事業形態と立地・周辺環境が合っていない場合も、審査で不利になる可能性があります。
面談
融資の審査では、融資担当者との面談が行われることが多いです。面談では、資料だけでは判断できない定性的な面や、資料で担当者が疑問に思った点などが質問されます。
なお、信用保証協会付融資では、金融機関との面談に加えて、信用保証協会との面談も行われます。ただし、信用保証協会の面談は初回時のみのことが多く、2回目以降は行わないことが多いといわれています。
【面談で聞かれる内容】
面談では、主に以下のような質問をされることが多いです。
- 代表者の経歴
- 事業内容
- 商品・サービスの内容やセールスポイント等
- 代表者個人の借入・返済状況
- 会社の資金繰り
- 事業計画
- 創業融資の場合は創業の目的等
これらの質問に対して事前に回答を用意しておくと、面談がスムーズに進みます。
特に、「計画通りにいかなかった場合どうするか」などの否定的な質問に対する回答や、データなどにもとづいた根拠のある回答を用意することが重要です。
また、回答が事業計画書などの内容と矛盾しないようにすることも大切です。
【面談の場所】
面談は、金融機関の店舗や事務所で行うケースと、融資担当者がこちらのオフィスに来るケースがあります。また、金融機関によってはオンライン面談が可能なこともあります。
【必要書類を忘れないように持参する】
面談では、本人確認書類や通帳をはじめ、いくつかの書類を持参するよう指示されます。これらを忘れると大きなマイナスとなるので、忘れないように持参しましょう。
4.契約・入金
審査に通ると、金融機関から電話やメールなどでその旨の連絡が来て、契約・入金手続きに進みます。
契約書や同意書などを提出しそれを金融機関が受理すると、その後数日程度で指定の口座にお金が振り込まれます。
契約の際は、契約書や同意書以外に、印鑑証明書や履歴事項全部証明書などを提出するのが一般的です。これらの書類をあらかじめ用意しておくと、手続きがスムーズに進みます。
信用保証協会付融資の場合
信用保証協会付融資では、各書類を金融機関と信用保証協会の両者に提出するのが一般的です。よって、契約の際は書類を2部ずつ用意する必要があります。
不動産担保融資の場合
不動産担保融資では、契約時に不動産の抵当権の設定と登記を行います。
登記手続きは金融機関が行うので、借り手は抵当権設定契約書の確認・同意や、登記手続きを金融機関が行うための委任状の記入などを行います。
会社の借り入れを成功させるポイント
会社の借り入れは審査に通らなければ利用できないので、成功させるポイントを押さえておくことが重要です。
以下のようなポイントを押さえて、借り入れが成功する確率を高めるようにしましょう。
- 財務健全性をチェックする
- 説得力のある事業計画書や資金繰り表を作成する
- 返済計画をきちんと立てる
- 粉飾決算は厳禁
- 決算書はできるだけ税理士に作成してもらう
- 設立直後の会社は創業融資などで返済実績を作る
- そもそも借り入れが必要か検討する
財務健全性をチェックする
会社の借り入れを成功させるために非常に重要になるのが、財務健全性です。
財務健全性とは、資金繰りがどの程度安定しており、経済的リスクに対応可能であるかを、財務諸表などをもとに評価したものです。
財務健全性の高さは、倒産リスクの低さや成長性の高さなどを意味しており、融資の審査で最も重視される点の一つとなります。
財務健全性は財務指標で評価する
財務健全性は、売上や利益が十分出ているか、負債が多すぎないかなどを見ることで、ごく大まかにチェックすることも可能です。
しかし、より正確に調べるためには、財務諸表から算出される財務指標を使う必要があります。会社の借り入れの審査でも、定量評価の際に財務指標が使われます。
財務指標にはさまざまな種類があり、それぞれ会社の収益性や安全性などを示します。下表は、主な財務指標を分類ごとにまとめたものです。
| 財務指標の分類 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 安全性に関する指標 | 返済能力や倒産リスクの評価 | 自己資本比率・流動比率など |
| 収益性に関する指標 | 効率的に利益を生み出しているかを評価 | 売上高総利益率・総資産利益率など |
| 成長性に関する指標 | 会社のこれまでの成長の実績や、将来の成長の可能性を評価 | 売上高増加率・純資産増加率など |
上表の財務指標の式と目安となる数値は以下のとおりです。
【自己資本比率】
- 自己資本比率(%)=(自己資本÷総資本)×100
- 業種にもよるがおおむね30%以上で健全とされる
【売上高総利益率】
- 売上総利益率(%)= 売上総利益÷売上高 × 100
- 製造業で平均19%程度、小売業で平均28%程度
【売上高増加率】
- 売上増加率(%)=(当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100
- プラスであれば前期より成長している
【財務指標の計算例】
ここでは最も基本的な財務指標の一つである、自己資本比率について例として紹介します。他の財務指標も、算出や評価の流れはおおむね同じです。
自己資本比率は、以下の式で定義されます。
- 自己資本比率(%)=(自己資本÷総資本)×100
ここで総資本とは、自己資本と他人資本の合計のことです。
- 総資本=自己資本+他人資本
自己資本とは返済の必要がない資本のことで、株主からの出資や利益の積み立て(利益剰余金)などが該当します。
そして、他人資本は返済の必要がある資本のことで、金融機関からの借り入れや社債などのことです。
高い自己資本比率は、返済しなくてよい資本を多く保有しており、返済の必要がある借金が少ないことを意味しています。
これは、借金に頼りすぎずに資金繰りができているということであり、倒産リスクが低いことを示唆しています。
このような流れで、財務指標によって財務状況を評価できます。
キャッシュフローの健全性も重要
キャッシュフローとは、会社に入ってきた現金と、出ていった現金の流れのことです。
売上高や利益には、売掛金などまだ現金になっていないものも含まれるため、利益が出ているのに現金が足りなくなるという状態になることがあります。
よって、財務状況を正確に把握するためには、実際の現金の流れを表すキャッシュフローも重要です。
キャッシュフローには以下の3種類があります。
| キャッシュフローの種類 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 営業活動に関する現金の流れ | 商品の売上や仕入れの支払いなど |
| 投資キャッシュフロー | 投資活動による現金の流れ | 設備投資や株の売買など |
| 財務キャッシュフロー | 資金調達と返済に関する現金の流れ | 融資の借り入れや返済など |
なお、キャッシュフローは、キャッシュフロー計算書で確認できます。非上場企業はキャッシュフロー計算書の作成は義務ではありませんが、作成したほうが財務状況を正確に把握できます。
【キャッシュフローの評価の仕方】
キャッシュフローを評価する時は、3つのトータルのキャッシュフローよりも、営業キャッシュフローがプラスであるかが重要になります。
これは、営業キャッシュフローのプラスは、本業で利益が出ていることを意味するためです。
逆に、たとえトータルのキャッシュフローがプラスでも、営業キャッシュフローがマイナスなら、過度な借り入れで財務キャッシュフローが増えているだけの可能性もあります。
財務分析ツールの活用
ネット上には無料で利用できる財務分析ツールがあるので、これを活用するのも良い方法です。ツールを利用することで、専門家でなくても財務健全性を手軽に評価できます。
ネット上で使える主な財務分析ツールには、経済産業省の公式サイト内にある「ローカルベンチマーク」や、日本政策金融公庫の公式サイト内にある「財務診断サービス」などがあります。
財務分析ツールでは、財務諸表の各数値を入力すると、安全性・収益性などの分野ごとに自動で分析して採点してくれます。
説得力のある事業計画書や資金繰り表を作成する
借り入れの審査において、財務諸表以外で重要になる書類が、事業計画書と資金繰り表です。説得力のある事業計画書と資金繰り表を作成することが、会社の借り入れの成功につながります。
事業計画書
事業計画書とは、事業の内容と今後の目標・計画などについて記載した書面のことです。
事業計画書に決まったフォーマットはありませんが、PDFやエクセルなどを使って、数ページほどの書面にまとめるのが一般的です。金融機関がフォーマットを指定している場合は、その様式に従います。
事業計画書に記載することが多い主な項目は以下のとおりです。
- 代表者の略歴
- 事業内容
- 取扱商品・サービスの概要
- 会社の組織図
- 自社の強み
- 経営課題とその対応策
- 業績の推移
- 必要な資金と調達方法
- 借り入れ状況
- 主な取引先・仕入先
- 事業の見通し
事業計画書は、収益が十分あり、借り入れを返済できることを示さなければなりません。そのためには、実現可能な目標と計画を、データにもとづいて根拠を持って記載することが重要です。
データは、公官庁などが公表している公式のデータを用います。例えばカフェ経営の場合は、「カフェの市場規模は、ここ数年は1兆1,000億円前後で推移」のように具体的に記載しましょう。
同業他社の売上規模などについては、公表されているデータがある場合はそれを用います。ない場合は、例えばカフェの場合なら、「A店はドリンク1杯400円前後で席数20」など、大まかな売上規模が推測できるデータを記載します。
資金繰り表
資金繰り表とは、現金収入と支出および残高の、過去の実績と今後数か月程度の予測値を月単位で記載する書面です。
フォーマットに決まりはありませんが、数値を記載する書面なのでエクセルなどで作成することが多いです。
資金繰り表では、下表のような項目について毎月の金額を記載していきます。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 収入 |
|
| 支出 |
|
| 経常外収支 |
|
| 財務収支 |
|
| その他の項目 |
|
資金繰り表は予測値も記載するため、予測値の算出根拠を明確にすることが重要です。販売計画や仕入計画などを立てて、実態に即した数値を算出する必要があります。
資金繰り表は、現金の流れを把握するという点で、キャッシュフロー計算書と似ている性質もあります。ただし、キャッシュフロー計算書は年度ごとの実績を記載するのに対して、資金繰り表は月単位で予測値も含めて記載する点などが違います。
返済計画を立てる
返済計画を立てなければ、会社の借り入れを成功させるのは困難です。
返済計画を立てるには、資金の使途と必要な借り入れ金額、および返済の元手(返済原資)を明確にする必要があります。
資金の使途を明確にする
返済計画を立てるためには、まず借り入れる資金の使途を明確にする必要があります。
「運転資金」「設備投資」のような漠然とした使途ではなく、例えば「〇〇の仕入れに××円」「内装工事に〇〇円」のように、使途と金額を明確にしましょう。
運転資金の返済計画
一般的に、運転資金は以下の式で見積もることができるとされています(手形取引がない場合)。
- 経常運転資金=売掛金+棚卸資産ー買掛金
手元の現金が経常運転資金に満たないと、資金ショートを起こす可能性があります。もし不足分を借り入れで補うなら、経常運転資金と手元の現金の差額が、借り入れるべき金額の目安となります。
運転資金の借り入れでは、返済原資は売掛金の回収と棚卸資産を販売した売上金で見積もるのが一般的です。
資金繰り表などから返済原資を見積もり、その範囲内で返済できるよう計画を立てます。
設備投資の返済計画
設備投資の場合は、取得した設備の減価償却費も含めて、「税引後利益+減価償却費」を返済原資と考えるのが一般的です。
事業計画書などをもとに、償却年数の期間にその設備がどれくらいの利益を生み出すかを見積もり、その範囲内で返済できるように計画を立てます。
返済シミュレーションを活用する
金融機関の公式サイトなどにある、返済シミュレーションを利用するのも有用です。
返済シミュレーションでは、借り入れ金額や返済期間などを入力すると、毎年の返済額や利息などが表示されます。
返済シミュレーションはあくまで簡易的なものですが、借り入れの申込みをする前に利用しておくと、おおまかな返済のイメージを掴むことができます。
粉飾決算は厳禁
融資担当者の印象をよくするために、粉飾決算を行う事例もありますがこれは厳禁です。粉飾決算は違法行為であるのに加えて、融資担当者にバレると借り入れが困難になります。
正しい決算書を作成したうえで、粉飾までして借り入れしなくてよい資金繰りを普段から心がけることが大切です。
また、決算書の作成を経理などに任せきりにしている場合は、経営者が把握していないところで粉飾が行われる可能性もあります。経営者自身か税理士などが定期的に帳簿をチェックするなど、不正対策を整えておくことも大切です。
決算書はできるだけ税理士に作成してもらう
小規模な会社や個人事業主は、決算書や確定申告書を自分で作成していることもあります。しかし、自分で作成するとどうしても不備が出ることがあるため、できるだけ税理士に依頼したほうがよいでしょう。
税理士に依頼すると、決算書などを作成するだけでなく、節税などのアドバイスがもらえるのも利点です。
個人事業主が税理士をつけるケースはあまり多くありませんが、例えば売上が伸びて課税事業者になったタイミングなどで、税理士をつけるといった方法も考えられます。
設立直後の会社は創業融資などで返済実績を作る
設立直後の会社はまだ返済実績がないため、借り入れの審査で不利になることがあります。そこで、創業融資を利用して早めに実績を作っておくと、後々大きな借り入れが必要になった時に有利になる可能性があります。
日本政策金融公庫や自治体の制度融資には、創業者向けの融資があります。これらの融資では事業計画などが重視されるため、実績がないことが不利な条件とはなりません。
ただし、創業融資の借り入れ後は、1年以上経過しないと追加の融資は難しいのが注意点です。
そもそも借り入れが必要か検討する
会社の資金調達手段には、金融機関からの借り入れ以外にもさまざまなものがあります。よって、資金が必要になったらすぐに借り入れを検討するのではなく、他の手段を比較検討してみることも大切です。
会社の資金調達手段は、おおむね「デットファイナンス」「エクイティファイナンス」「アセットファイナンス」の3つに分類されます。これらの違いを理解したうえで、自社の状況に適した手段を選ぶことが重要です。
デットファイナンス
デットファイナンスは負債を増やすことによる資金調達方法で、金融機関からの借り入れや社債の発行などが該当します。
デットファイナンスは利息をつけて返済しなければならないのがデメリットですが、返済額が決まっており資金計画が立てやすいなどのメリットがあります。
デットファイナンスは、まとまった資金を比較的短期間で調達したい時などに有用です。
エクイティファイナンス
エクイティファイナンスは資本を増やすことによる資金調達方法で、株式の発行による資金調達を指します。
エクイティファイナンスの代表的な手法には、株主割当増資や第三者割当増資などがあります。他にも、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルのような、出資により利益を上げることを専門とする者から出資を受ける方法もあります。
エクイティファイナンスは返済の必要がないのがメリットですが、出資者に経営介入される場合があることなどが注意点です。また、株式を発行しなければならないため、個人事業主は利用できません。
エクイティファイナンスは、長期的な事業拡大を目指したい時や、財務基盤を強化したい時などに有用です。
アセットファイナンス
アセットファイナンスは手持ちの資産を利用した資金調達方法で、遊休資産の売却やファクタリングなどが該当します。
ここでファクタリングとは、売掛債権をファクタリング業者に譲渡して、支払期日前に現金化する資金調達手段のことです。借り入れ以外の資金調達として、中小企業でも利用しやすい手段の一つとなっています。
アセットファイナンスは資産に価値があれば利用できるため、会社の信用が低くても利用できることなどがメリットです。また、資産の売却はいわゆる「オフバランス化」になるため、財務体質の改善などの効果があるともいわれています。
一方、価値があり流動性のある資産を保有していないと利用できないことや、その資産が将来生み出すかもしれない利益を放棄することなどが、アセットファイナンスの注意点です。
その他の資金調達手段
上記の3種類に該当しない資金調達手段の例として、補助金・助成金やクラウドファンディングなどがあります。
【補助金・助成金】
補助金・助成金とは、国や自治体が、条件を満たす事業者に対して資金を給付する制度です。
補助金は設備投資など比較的大きな金額を支給する制度で、事業計画などが認められて採択された事業者しか利用できないという特徴があります。
そして、助成金は雇用改善などの比較的少額の支給を行う制度で、条件を満たせば原則として支給されるのが補助金との違いです。
補助金・助成金は、返済の必要がないのが大きなメリットです。一方、事業の進捗状況を随時報告しなければならないなど、手続きが面倒な傾向があるのはデメリットといえます。
また、支給は原則として事業の完了後になるため、つなぎ資金が必要になることも注意点です。
【クラウドファンディング】
クラウドファンディングとは、主にネットを使って不特定多数の人から資金を募る調達方法です。
魅力的なプロジェクトを提示することで支援者を募り、支援者は見返りとして返礼品を受け取ります。
クラウドファンディングは会計上は商品・サービスの売買と同様に処理されるため、借り入れや株式の発行などとは別種の資金調達方法となります。
ただし、クラウドファンディングには株式投資型や貸付型もあり、これらはそれぞれエクイティファイナンスやデットファイナンスに該当します。
クラウドファンディングは魅力的なプロジェクトがある場合は有用な資金調達手段である一方、支援者が集まらないと資金調達できないのが注意点です。
まとめ
会社の借り入れには、プロパー融資や信用保証協会付融資を始めさまざまな種類があり、借り入れできる金融機関も銀行や信用金庫を始めさまざまです。これらの違いを理解して、自分に合った借り入れ手段を選びましょう。
また、会社の借り入れは審査に通らないと利用できないので、財務健全性のチェックや説得力のある事業計画書の作成などを実践して、借り入れの成功率を高めることが大切です。
会社の借り入れについて正しく理解して、安定した資金繰りを実現しましょう。